スポンサーサイト
蔵開きに行きました!
2009年02月08日
今日は朝、5時半起きでした。
と言うのが、しげますの蔵開き に行ったからです。
6時頃でないと、蒸した米をこうじ室に入れるのを見学出来ないからです。
下の写真は、蒸した米をしょうけに入れて冷えないように
人力で全速力で行く場面です。


運ばれた蒸した米は、こうじ室に運ばれます。
ここで広げて冷まして(32度くらい)麹菌をふって植えつけます。
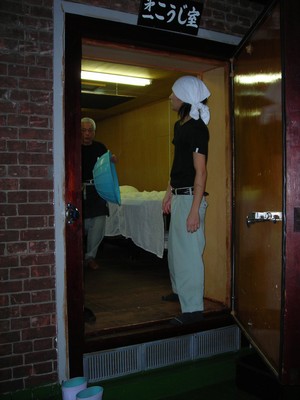
今年の使用している米は、酒作りに適しているので良い酒が出来上がっているそうです。
(去年の使用の米は、少し硬かったそうです。)
1717年創業のしげます 高橋商店は、12名で、去年の11月から
今年の3月まで蔵に泊まって、昼夜をとわず、酒作りに取り組みます。
酒作りの使う米です。糸島で作られる山田錦などです。

酒の出来る工程は、玄米を精米→洗米→浸漬→蒸米→製麹→酒母→もろみ
→圧搾→滓(おり)引き→濾過→火入れ→貯蔵→ビン詰めです。
このような過程を経て出来上がった今年の酒を試飲しました。
作りたての生酒は、とても美味しくて、ついつい飲みすぎました。
最近は、焼酎を飲む人が多く、日本酒の消費が減っているようです。
美味しいお酒と食事は、セットで楽しみたいものです。
と言うのが、しげますの蔵開き に行ったからです。
6時頃でないと、蒸した米をこうじ室に入れるのを見学出来ないからです。
下の写真は、蒸した米をしょうけに入れて冷えないように
人力で全速力で行く場面です。
運ばれた蒸した米は、こうじ室に運ばれます。
ここで広げて冷まして(32度くらい)麹菌をふって植えつけます。
今年の使用している米は、酒作りに適しているので良い酒が出来上がっているそうです。
(去年の使用の米は、少し硬かったそうです。)
1717年創業のしげます 高橋商店は、12名で、去年の11月から
今年の3月まで蔵に泊まって、昼夜をとわず、酒作りに取り組みます。
酒作りの使う米です。糸島で作られる山田錦などです。
酒の出来る工程は、玄米を精米→洗米→浸漬→蒸米→製麹→酒母→もろみ
→圧搾→滓(おり)引き→濾過→火入れ→貯蔵→ビン詰めです。
このような過程を経て出来上がった今年の酒を試飲しました。
作りたての生酒は、とても美味しくて、ついつい飲みすぎました。
最近は、焼酎を飲む人が多く、日本酒の消費が減っているようです。
美味しいお酒と食事は、セットで楽しみたいものです。


